青谷梅林 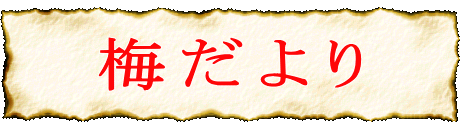
青谷梅林の歴史
青谷梅林は、青谷地区東方の丘陵地を占め、天山を中心として北の播磨崎・堂山・南の石神・百間場にわたって在り更に青谷川を隔てて、その南の大谷・白坂に及んでおり老樹古木をまじえて数万本の梅樹が群生していたと伝えられている。
青谷梅林の起源については、明らかでないが、後醍醐天皇の皇子宗良親王の歌に「風かよふ 綴喜の里の 梅が香を 空にへだつる 中垣ぞなき」とあることから、鎌倉末期ごろは既に梅林の在ったことが知られる。
徳川時代に淀藩から梅樹栽培の奨励を受け、大いに植樹されたと『青谷村誌』に伝えられている。明治33年(1900)青谷梅林保勝会を設立して梅林の保護と宣伝につとめてから、花見客は多くなり名勝地となった。
青谷梅林の特徴
現在、およそ20ヘクタールの面積に梅樹が植えられており、主な品種は城州白(梅菓子・梅干・梅酒用等)、白加賀(梅酒用)、オタフクダルマ(小梅)、青軸、鶯宿、玉英などがある。毎年6月から7月にかけて約120〜130トンが収穫される。また、2月から3月にかけては、約1万本の白梅が咲き誇り青谷は、大きな白布を広げたように白一色となり、どこまでも梅の香りにつつまれる感じになる。